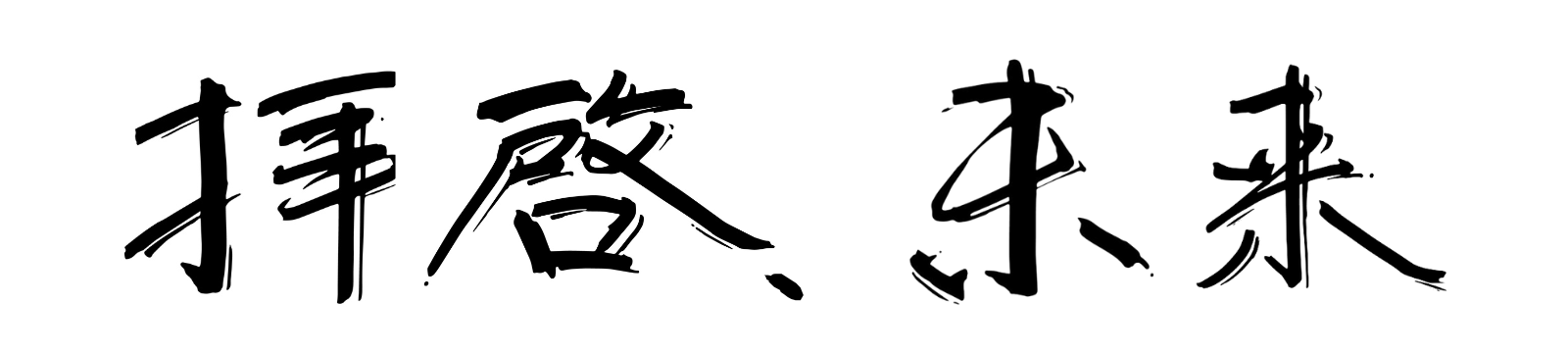取材:柴田涼平 執筆:三川璃子
3年前に当メディアの取材を受けてくださった久保匠さん。
現在、道内・道外、営利・非営利のバランスを保ち、クライアント約30社に対し、事業づくりや資金調達、組織マネジメント、その他プロジェクトのマネジメントの支援をしています。年々活動の幅が広がり、2025年には法人化され「株式会社すくらむ」が設立されました。
ーー「ローカルの最前線に立って課題に向き合うことが、社会的インパクトにつながっていく」
久保さんは、その最前線で活動しながら、地域と社会、行政と民間をつなぐ役割を果たしてきました。本記事では、久保さんが「ローカルインパクト」という考えに至るまでの背景や、具体的な取り組みを紹介します。
▼前回の記事はこちら


ローカルからソーシャルへ。たどり着いた「ローカルインパクト」という言葉

――3年前の取材以降、どんな変化がありましたか?
大きく三つの変化がありました。
一つ目は、『ローカルインパクト』という考えが自分の中に定着したことです。以前からソーシャル領域で活動してきましたが、どのような役割を果たしていくかを考える中で、いきなり“ソーシャルインパクト”を生み出すのは難しいと感じました。世界規模や日本全体の課題を一気に解決するようなインパクトは、すぐに達成できるものではありません。
まずは課題の最前線であるローカルの現場で実践を積み重ね、そこにあらゆるリソースを投入しながら事業をつくり、PDCAを回す。その過程で生まれるローカルインパクトこそが、完全な横展開は難しくても、他の地域の参考になり、最終的にソーシャルインパクトにつながるのだと考えるようになりました。この考えが腑に落ちて以来、ローカルインパクトという概念が非常に重要だと感じています。ローカルだから小さくてもいいのではなく、むしろ社会を変えていくために、ローカルの最前線でまず実践していくことが、自分にとって最も大切な価値観になりました。

二つ目は、ファンドレイザーとして独立した後、「狭義の資金調達」だけでなく、インパクトを生み出すビジネス構築、セクターを横断した事業想像、そして自らも投資家として資金提供を行うこと等、資金を軸としながらも多様な役割を担うようになったことです。ここ2、3年で、自分の関わり方の幅が広がったと感じています。
三つ目は、以前は自分のことをコンサルタントと捉えていましたが、最近はその肩書きに違和感を持つようになりました。今は、自分がワクワクする事業を生み出し、手を動かし、頭を使い、自らも出資して創り上げていくことに魅力を感じています。当事者として事業に関わることこそが、一番楽しく、かっこいいと感じるようになりました。
※1ソーシャルインパクト:特定の活動、プログラム、プロジェクトが社会や環境に与える影響を指します。 従来は非営利団体や社会的企業の活動として重視されてきましたが、近年は企業活動においても欠かせない概念となっています。
※2ローカルインパクト:地域における事業や活動が社会や環境に与える影響を指します。
――「ローカルインパクト」という言葉にたどり着いた経緯を教えてください。最初は「ソーシャルインパクト」という言葉を使っていたのでしょうか?
そうですね。当初は『ソーシャルインパクト』という言葉を使っていました。ただ、それは特別こだわっていたわけではなく、3年前は、ソーシャルインパクトのプロセス全体の解像度が低かったのだと思います。
ソーシャルインパクトがどこで何が始まり、どのように広がっていくのかを考えるようになり、徐々に仮説を立てられるようになりました。『ローカルインパクト』という言葉を使うようになったのは、そうした理解が深まったからですね。
―― その考えを強く持つようになった背景には、具体的な取り組みがあったのでしょうか?
これまでの自分のキャリアと関係していると思います。最初は福祉の現場で働いていて、物理的にローカルに密着した仕事をしていました。そこでは、目の前の人々の変化や関係性の変化を直接見ることができました。その後、日本ファンドレイジング協会で働き、ファンドレイジングを通じてソーシャルインパクトを生み出す仕組みづくりに関わる仕事をしました。ここでは、大きなやりがいを持ちつつもローカルの現場に直接関わる機会がほぼなく、その距離感に葛藤を感じることもありましたね。
しかし、この二つの立場を経験したことで、どちらか一方に偏るのではなく、両方をつなぐことの重要性を実感しました。そして、その役割を果たすことに意味があると確信したんです。

――ローカルインパクトとソーシャルインパクトの両方を理解し、橋渡しできる人材は貴重だと思いますが、そうした人は一般的に多いのでしょうか?
表面的には存在すると思います。ただ、単に両方のコミュニティに所属すればいいというものではなく、それぞれに異なる視点を提示し続けることが大切だと考えています。
例えば、マクロな視点を持つ人には『もっとローカルを見ましょう』と伝えます。全国的な政策や動きも、その最初のデータはローカルで取られていることが多いですよね。だからこそ、ローカルを見ながら、意味のある施策を打つべきだと。
一方で、ローカルの人たちには『もっとマクロを意識しましょう』と伝えます。地域内だけでお金を回すのではなく、外部から資金を調達することも必要ですし、全国的なノウハウを活用することも大切です。そして自分たちの実践が、社会を変える可能性があるという視点を持つことが重要です。
僕は、両方の立場に対して忖度せず、異なる視点を伝え続けることを決めています。それは共感を得られないことも多く、正直しんどいことも多いですが、それでも一貫性を持って取り組んでいます。
――この領域で活動するには、かなりタフさが求められますね。
マクロの視点を持つ人にミクロの重要性を、ミクロの視点を持つ人にマクロの重要性を伝えるのは、時間がかかる上に、相手のプライドもあってすぐには受け入れられないことも多いですよね。いわば費用対効果の悪い取り組みだと思います。
まさにその通りで、効率的とは言えません。でも、そこにしっかりと時間を使いたいからこそ、他のことはできる限り効率的にできるように心がけています。

ーー自ら出資して事業を作るという選択肢も増えたと思いますが、それが実際に始まって、今どんな心持ちですか?
ファンドレイザーとして「社会のお金や人のお金を集め、それをインパクトへ投資する」仕事をしてきました。でも、どうしてもお金が集まりにくい領域もあるし、設計から資金調達を経て事業を実行するプロセスは時間がかかる。その点、自分でお金を出して事業を立ち上げる方が圧倒的にスピード感があります。
とはいえ、私の資金だけでは何千万単位の資金を常に出資し続けることはできない。だからこそ、「できないからやらない」ではなく、できる範囲からでも自分で資金を投資して事業を生み出す経験を積むことを意識しました。
その第一歩が、 株式会社とける への出資でした。最初の経験として、会社の株を持たせてもらい、出資をする機会を与えていただきました。これは単なるコンサルタントとしての関わり以上に、組織や事業の成長にコミットする重要な経験になりました。単なる契約関係ではなく、中長期のインパクトを共に生み出すことを意識するようになった瞬間です。
この経験を経て、さらに中札内村で行った※SIB型事業 では、自分で事業費を全額出資する形を試しました。これはまだ現在進行中ですが、こうした実践の中で「自分でお金を出す」という意識が育っています。
※SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド):行政と民間が連携して社会課題を解決するための事業スキーム。
ーー以前の取材から、「受益者ファースト」の考え方を一貫して大事にされていると感じていますが、この考え方はやはり変わっていないですか?
変わらないですね。ただ、受益者の視点から見た地域課題と、もう少し広い視点から見た地域課題は異なるし、受益者も一人ではない。だからこそ、多面的に見る視点を意識するようになりました。でも、基本的な考え方は変わらないですね。
町の限られた予算の中で障害福祉計画に沿って事業を組み立てていきます。仮に、障害のある方への支援枠組みを広げるために予算を増やしたとします。でも、町の税収は限られているので、その分、たとえばコミュニティバスの運営費が削られることになり、高齢者の移動問題が深刻化するかもしれません。
時間もお金も有限だからこそ、どの視点から見るかでリソースの再配分や適切なバランスが変わってきます。もちろん、すべて税金で賄うのではなく、ここは民間資金でまかなえるかもしれない、ここはどうしても公的資金が必要だから頑張ろう、というように、ファシリティマネジメントをしていくことが大事です。

ただ、個別の受益者と向き合うことは重要ですが、それだけでは、「誰かの幸せが、誰かの不便を生む」可能性がある。それは避けたいですよね。だからこそ、「無邪気に受益者ファーストを掲げるだけでは不十分だ」と思っています。受益者も含めたウィンウィンの関係をつくる視点が必要なんです。
社会が変わるためにまずは「自分」が動く。仕組みづくりの葛藤と喜び
ーー 仕事の中でやりがいを感じる瞬間と苦労する瞬間についても聞きたいです。
プロジェクトの定量・定性目標を達成した瞬間は嬉しいですね。
あとは、ローカルからソーシャルへの道筋が見えたとき。これは案件の要件定義のタイミングで気づくことが多いです。例えば、株式会社とけるが開発している事業を通して、世の中の健康経営の常識を変えられるのでは? といった道筋が見えた瞬間。それがひらめいて、実際に形にしていくときが楽しい。
具体的には、契約の瞬間ですね。ただのお金のやり取りではなく、ローカルインパクトやソーシャルインパクトの方向性をお互いに確認し、中長期で目指していこうと決めたとき。パートナーと「一緒にやっていこう」とワクワクしますし、やりがいを感じます。
ーー 逆に、苦労するのはどんなときですか?
例えば、ファンドレイジングだけでは本質的な課題解決につながらない場合はあること。お金は集められるけど、課題解決に向けての設定が甘いと「8歩進んで10歩下がる」みたいな状況になることもある。資金調達のために誰かが消耗することもあって、そういう仕事はやりたくないなと思います。
解決すべき課題を設定し、ステークホルダーと一緒に目的と目標を決め、インパクト戦略、ビジネスモデルを組み立てていく。でも、そのプロセスにお金がつくかどうかは別の話。そこが難しいんです。このように「必要なプロセスにお金がつくとは限らない」。それは正直、もどかしい部分ですね。
ローカルインパクト型の事業は、ここが本当に難しいところです。

ーー そこは、今後変わっていく兆しはありますか?
市場の整合性だけで考えると、現状はあまり変わらないので悲しくなりますね。でも、「どうやったら変えられるか?」を考えたときに、自分で資金を出すことも含めて、地域・社会のお金の流れを変えることが必要だと思っています。
実はつい先日、『インパクト・キューブファンド』を組成しました。ローカルインパクトの領域では、様々な財源を組み合わせてトータルで必要な資金を調達するケースが多いです。だからこそ、地域から社会を変える戦略をつくり、様々な資金を集めるための「触媒となる最初の資金」が必要だと思ったのです。その触媒資金を自分たちの意志で投資できることで、スピード感を持ってインパクト創出に取り組めると考えたからです。とはいえ、個人で出せる金額には限りがあります。
そこで、自分を含む3人で共同型資金拠出の仕組みを構築しました。また、資金投資だけではなく、経営や事業運営に貢献するのが特徴です。事業創造支援、社会的インパクトマネジメント支援、バックヤード支援、コミュニティ資金調達支援など、共同代表3人の強みを活かして、投資先とともに成長する仕組みです。
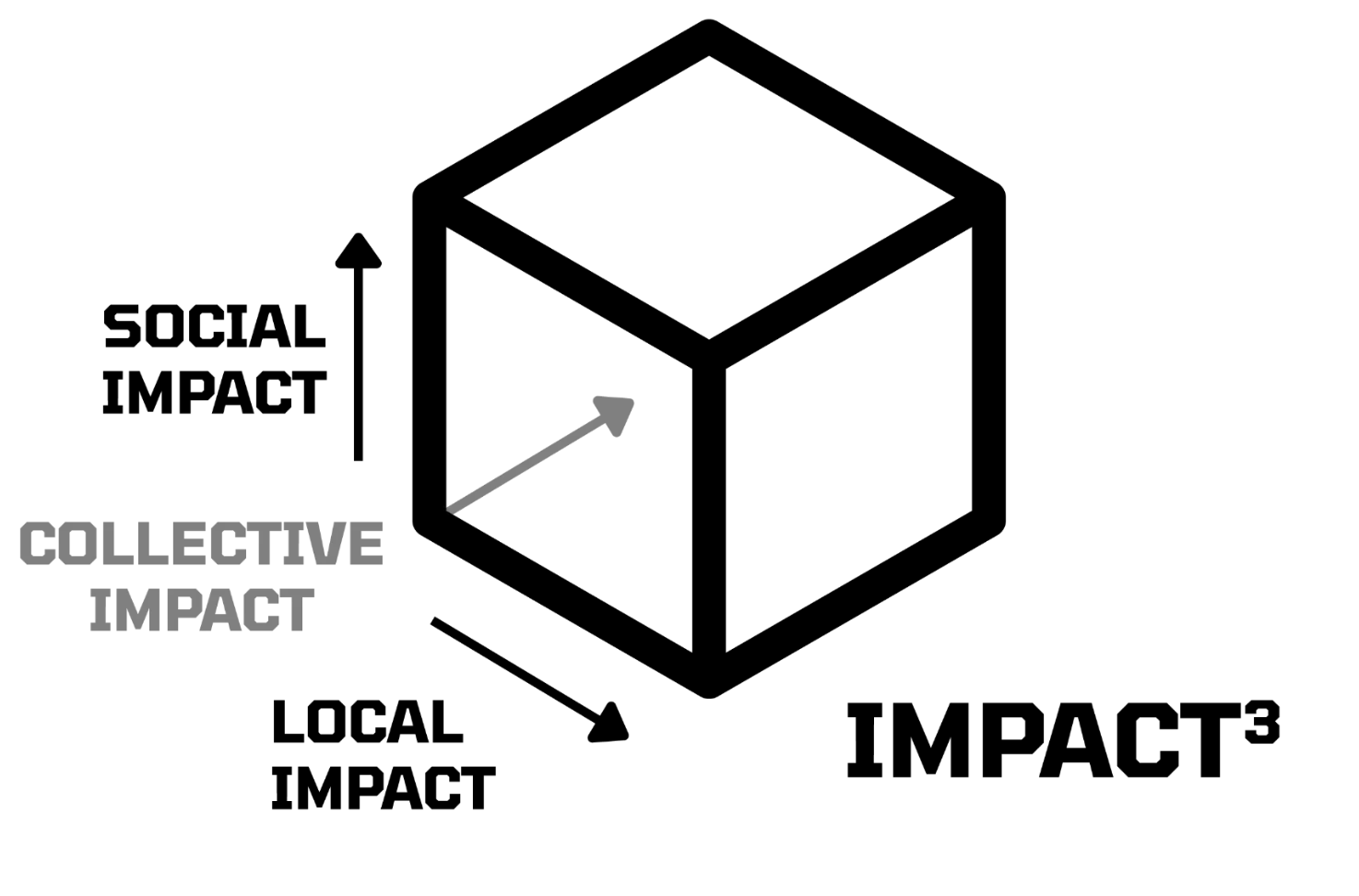
この取り組みを継続・発展させることで、実績が生まれ、より洗練された仕組みが構築されると思います。このように、お金に意志を灯し、ローカルインパクトに投資する文化を、少しずつ創っていきたいです。
▼3月にリリースしたばかりのファンド『インパクト・キューブファンド』
行政と民間、それぞれの価値観の違いを乗り越え、未来を想像する
ーーこの仕事を続けていてよかったと思うエピソードがあれば教えてください
ローカルインパクトを創出する上で、共通の言語や価値観を持っていない人たちと協力しながら、目的や目標を設定して進める場面で、そのプロセスがうまくいった瞬間は嬉しいです。
特に印象的だったのが、中札内村で実施しているSIB(ソーシャルインパクトボンド)を活用した官民連携型事業です。村全体のヘルスケアを推進する新たな仕組みを構築するための取り組みです。これは、行政と民間が一緒になってインパクト指標を設定し、それを達成するための事業を設計します。事業費は民間の資金提供者が事業開始時に全額投資し、それが達成された場合に行政から資金提供者に配当を乗せて資金がリターンされるという仕組みです。これは北海道初の事例として多くの方に注目していただき、現在目標達成が見込まれています。来年度はさらに大きな規模で、外部の資金提供者に関わっていただける可能性も出てきました。北海道初のチャレンジに、資金提供者であり、プロジェクト伴走支援者として携わることができて、本当に良かったと思っています。
▼参照記事:【北海道初のSIBを実施】成果連動型民間委託契約ソーシャルインパクトボンド(SIB)を導入して運動無関心層に着目した運動プログラムづくりを北海道十勝中札内村から。

ーー中札内のSIBについてですが、例えば行政コストが5000万円かかっていたものを、仕組みを作ることで2000万円に削減するというのがSIBの良さですよね。
そうですね。ただ、行政コストは一気に減るものではなく、短期的な目標を積み上げていくことで、中長期的に大きな削減へとつなげていきます。
一番のポイントは目的と目標の設定だと思っています。
例えば、運動無関心層にプログラムを届けて、最終的に健康促進につなげるといった形です。対象を絞ることに対しては賛否がありますし、「何人に届けるのか」「何回実施するのか」といった定量的な目標を明確にしないと、投資スキームは成立しません。
行政は幅広い人に届けることを重視し、民間は具体的な事例を作ることに注力するため、考え方が異なります。そのため、お互いの主張をぶつけ合うだけではなく、どちらの強みを活かせば突破できるかを論理的に考えることが重要でした。

当事者同士で客観的な視点を持ち続けるのは難しい可能性があるので、私は伴走者として関わり、互いの強みを活かし合える仕組みづくりに貢献できるように努めました。また、資金提供者として、この目的・目標達成にとって最適な資金提供スキームを検討した結果、SIBにたどり着きました。このプロセス全体が、嬉しかった経験であり、大変だった経験でもあります。
ーー民間と行政の価値観をすり合わせるのはなかなか大変ですよね。
どちらが主導するのか、どう相互作用を生み出すのかを考えるのが大きな課題でした。短期的に見ると、僕は民間が柔軟に動くほうが良いと考えています。行政は性質上、柔軟な計画設計や変更が難しい場合があるので、中長期目標が一致しているなら、まずは素早く柔軟に動ける民間がフレキシブルに動くのが良いと感じています。そのうえで、連携関係を強め、最終アウトカムにつなげていくのが理想です。
ーー社会課題の解決に関わる人にはどんなスキルやマインドセットが必要だと思いますか?
まず、課題解決には課題設定が不可欠です。例えば、医療が必要な人に医療を届ける前に、そもそも医療が必要ない状態にする「予防」が重要ですよね。このように、どれだけ根本的な課題にアクセスできるかが鍵になります。
とはいえ、対処療法を否定するわけではありません。たとえば、ゴミ問題を考えると、ゴミが出ない仕組みを作ることが重要です。しかし、目の前にゴミが落ちているなら、まずはゴミを拾うことから始めなければいけません。この両方の視点を持つことが大切だと思います。
“ソーシャル”というと「良いことをする」「多様な人を受け入れる」というイメージがあります。私もその包摂性に救われた一人です。一方でより良い地域や社会の実現に貢献したいのであれば、人一倍努力してスキルを磨き、重要な場面で力を発揮できる存在であることが重要だと思います。この領域は、まだ社会に無い仕組みを創造したり、ゼロから市場を切り開いていく必要があるため難易度が高いと思います。私もまだまだ力不足を痛感する場面が多く、もっともっと努力を積み重ね、常に自分をアップデートし続けなければ、いつ役割が無くなってもおかしくないと考えています。

さらに、ローカルとソーシャル、抽象と具体を往復できる力も重要です。異なる価値観や背景を持つステークホルダーをマネジメントし、共通の目標を設定して、事業を組み立て、資金を集め、組織を動かす。こうしたマネジメント力が求められると思います。
そして最後に、「実践」が何より大事かと。実践の場をどう確保するかが難しい問題ですが、たとえば若手が失敗できる環境を作ることが重要だと考えます。最初は無償でもいいから実践の機会を得て、そこから経験を積む。こうした実践の場がもっと増えるといいなと思います。
ーー確かに、その環境をどう作るかが鍵になりそうですね。
みんなで手を取り合い、課題に向かって「すくらむ」を組めるように
ーー今後の展望について、これからどんな社会の変化を目指していますか。
「ローカルインパクトからソーシャルインパクトを生み出す」というビジョンを掲げています。具体的には、まず3年間で10の成功事例をつくることを短期的な目標としています。
例えば、富山県の「一般社団法人SMARTふくしラボ」の取り組みがあります。高齢者社会の課題をテクノロジーで解決するプロジェクトが注目されていますが、技術やビジネスモデルがあっても、住民理解や制度の規制といった「目に見えないソフトの部分」がボトルネックとなることが多い。その技術(=ハード)と、ソフトを繋ぐ仕組みづくりを構想しています。

また、沖縄県では株式会社うむさんラボが主体となる「県民ファンド」を構想しています。例えば県民が毎月100円ずつ寄付をして、それを沖縄をよくするための事業を行っている社会起業家に助成や投資という形でお金を託すという構想です。地域の課題解決に寄付や投資を行うことで、「お金を通じて参加」し、受け取った起業家も県民の想いを背負って精一杯事業に取り組む。このような「参加型のお金の流れをデザインする」ことが重要だと考えています。
さらに、「テーマ軸」にも注目しています。例えば、北海道の健康課題やジェンダーギャップの解消といったテーマを軸に、ローカルから全国へ発信するプロジェクトも進めています。
これらを総合して、「地域」、「テーマ」、「資金循環デザイン」という3つの軸で、ローカルインパクトを生み出すプロジェクトを10個つくることが、短期的なコミットメントです。
ーー活動を通し、多くの人々が主体的に行動し、社会を変えていく流れを生み出そうとしているのだなと感じました。
副次的な成果としては確かに意識しています。地域の課題解決に取り組む中で、結果として人々の主体性が育まれる。
このように、ローカルインパクトがソーシャルインパクトへとつながる仕組みを、具体的な事例を通じて確立していきたいと考えています。
域内外の資金を地域で循環させる仕組みを整え、そこで生まれた資金を新たな課題解決に活用する。そんな地域資源・資金循環デザインに挑戦したいと考えています。
――地域資金循環ですね。改めて素晴らしい取り組みだと感じます。その取り組みによって派生的に生まれる変化も多いでしょうね。ミクロとマクロの両方を経験し、大切にしてきたからこそ語れる視点ですね。

――最後に、未来に残したいものの変化について、今どのように考えていますか?
ローカルインパクトがソーシャルインパクトへと発展し、社会を変えていくことです。自分が住む地域がより良い場所になれば、自分自身も、周囲の人々も幸せになれる。その循環を信じて取り組んでいます。
未来に残る仕事をしたいという思いが、最近ようやく明確になってきました。
「すくらむ」という名前の由来についてなんですが上川教育局が推進し、各地域の特性に合う形で活用されている『個別の支援計画「すくらむ」』に由来しています(育ちと学びの応援ファイル「すくらむ あさひかわ」)
保育園、福祉施設、学校、障害当事者の親の会などが連携し、地域全体で子どもを支えるための計画です。例えば障害のある子どもや支援が必要な子どもを、一つの機関だけでなく、多様な専門機関がスクラムを組んで支える。実は、このプロジェクトの事務局を担当していたのが私の父なんです。
地域の多様な関係者と連携しながらインパクトを生み出すことを目指した取り組みで、父は教育委員会に所属しながら、多くの専門家に声をかけ、支援を広げていった。その姿勢に、私は無意識のうちに影響を受けていたのかもしれません。
――素敵な話ですね。まさか、自分が父親の意志を継ぎ、その名前を会社名にまでし、ローカルインパクトからソーシャルインパクトを生み出す役割を担うことになるとは、想像もしていなかったのでは?
本当に、当初は全く考えていませんでした。父は現場の教員から始まり、特別支援学校、教育委員会、そして校長まで務めました。一方、私は教育分野ではなく、まったく異なるキャリアを歩んできました。でも、長期的な視点で見れば、共通する部分があるのかもしれません。
屋号が必要になったタイミングで、この名前にしようと決めたんです。独立する際に、やはりこれしかないと思いました。
――父親に対するリスペクトが強くあったんですね。
そうですね。ただ、こうした取り組みは簡単には伝わりにくいものです。専門性が異なる人々と対話しながら、共通言語を探り、連携を作っていく。そのプロセスの難しさは、大人になってようやく実感できるものだと思います。しかも、当時は今ほどプロジェクトマネジメントの体系化が進んでいなかった時代ですから、父がやっていたことの価値がより鮮明に見えてきます。
僕も同じ意志をもちながら、今やっている仕事を未来に残していきたいなと思っています。
「ソーシャルインパクト」という言葉が広がり、社会課題の解決策として知られるようになりました。しかし、課題の全体像を把握することは容易ではありません。私たちはマクロな視点に目を奪われがちですが、社会課題の最前線はローカルにあります。
地域に根ざした課題解決の取り組みは小さく見えるかもしれませんが、地域での実践を通して得られた知識や経験は、他の地域にとっても有益な示唆となるはず。株式会社すくらむが取り組む地域での成功事例は、全国的な課題解決の道筋を示してくれるのだと感じます。
「ローカルからソーシャルへ」この言葉は、地域から社会へ、希望を繋ぐ合言葉になっていくでしょう。
インタビュイー:久保匠(くぼ たくみ)
株式会社すくらむ 代表取締役CEO
1993年北海道旭川市生まれ。大学卒業後、愛知県知多半島に拠点を置く福祉系NPO法人に就職し、障害者支援に携わる。
2018年4月より日本ファンドレイジング協会に参画し社会課題解決に取り組む法人のファンドレイジング戦略策定支援を担当する。
2022年1月より独立し、ソーシャルビジネス、インパクトスタートアップの資金調達、事業創造、社会的インパクトマネジメント、クロスセクター連携創出を行っている。
また、投資、融資、助成金資金提供業務、Social Impact BondやPay for Successを活用した成果連動型の公民連携事業にも取り組む。
様々なスタートアップや非営利組織の役員・アドバイザー、中京大学講師、経済産業省 北海道経産局事業『成長型中小企業等研究開発支援事業 オープンイノベーション・技術開発促進事業』専門家等も務める。
■公式サイト:https://li-scrum.com/
■公式SNS: Twitter / Facebook