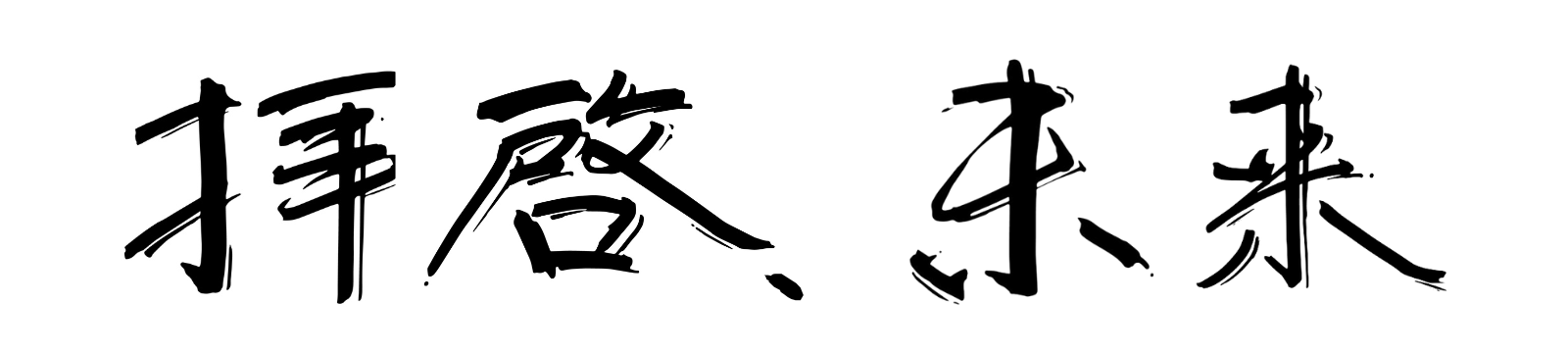取材:柴田涼平 執筆:谷郁果
──あなたが未来に残したいものは?
「ゴールに辿り着くまでの失敗も成功も残していきたい」
そう語るのは、合同会社ジモトファブの代表・土山俊樹さん。地域おこし協力隊としての任務を終え、次へのステップを踏み出しています。
| 合同会社ジモトファブとは、栗山町の委託のもと、ものづくり工房「ファブラボ栗山」を運営する会社。デザインの代行事業や、ファブラボ栗山での教室事業も手がけています。 |
札幌出身の土山さんは栗山町との出会いから、地域おこし協力隊へ。そして会社設立に至るまでには土山さんの”ものづくり”に対するアツい思いがありました。
※取材の様子は2022年秋ごろ、栗山煉瓦創庫くりふと移転前のものです。
栗山でつくり始める、ものづくりの土壌
──最初に、土山さんの経歴を教えてください。
網走で生まれ、札幌で育ちました。小さい頃から絵を描くのがすごく好きだったこともあり、札幌市立大学デザイン学部に進学、プロダクトデザインを専攻しました。
当時は、カーデザイナーになりたかったんです。大学3年生のときには、有名な自動車メーカーのインターンシップにも行きました。でもそこで打ちのめされましたね。周りはみんな名高い美大の学生。僕だけがその場に必要なスキルが伴っていないことを痛感しました。
普段からまじめな学生ではなかったのですが、一気にやる気も失って、大学の卒業もぎりぎり。就活もしてなくて、お世話になった先輩に声をかけていただき、札幌の工作機械を貸し出す工房を運営する会社に入社しました。
たまたま縁があって入社できた場所でしたが、当時は前例のない新しい事業形態だったので、いろんなスキルや経験を得ることができました。また、工房を利用するクリエイターの方々と知り合えたし、中には今でも付き合いのある方もいます。すごく面白い場所だったのですが、1年もたたず閉店してしまいました。僕の感想になりますが、当時東京からきたこの事業は、札幌圏で活動するクリエイターに対してサービス内容や料金形態、立地的にも根付いていなかったように思いました。

そんな状況で途方に暮れていたときに、社長から台湾で働かないかと誘われました。以前、社長の似顔絵を描いて喜んでいただいたことがあったのですが、まさか台湾で似顔絵を売ることになるとは思いもしませんでした。お客さんの似顔絵をデジタルデータに変換して、スマホケースやがま口ポーチに印刷した商品を販売していたのですが、これが予想以上に売れたんです。自分でもびっくりでした。
「今度は東京にこないか」という話もあったんですが、地元の北海道に戻りたい気持ちもあって断ることに。
「でも北海道で何しよう?」と悩んでいた時にたまたま見つけたのが、栗山町の「ファブラボ栗山」という工房の担い手としての地域おこし協力隊の募集でした。
──そこからすぐに協力隊に応募されたのですね。
いえ、最初は渋りました。募集要項を見て、正直この事業がうまくいくとは思わなかったんです。札幌で同様の事業の運営もうまくいかなかったのに、栗山ではなおさら難しいんじゃないかと不安になりました。
でも募集内容をよく見ると、研修内容に「ファブラボ鎌倉」での1年間の研修があることを知ったんです。この「ファブラボ鎌倉」っていうのが、日本ではじめて工作機械を貸し出す工房をつくったところで。
僕自身、工房事業のスタッフとして経験は積んでいると自負していましたが、その元祖である「ファブラボ鎌倉」で修行できるものならしてみたいという思いで応募しました。
また、将来的には自分の工房を持ってみたいという想いもあったので、すごく良いきっかけでした。
「ジモト」を盛り上げる人たちと、まちの未来を開拓する
ファブラボ栗山の担い手として協力隊を務めた土山さん。退任後も夢であった工房を運営するために栗山町で会社を立ち上げます。
──地域おこし協力隊を終えてもなお、合同会社を立ち上げて「ファブラボ栗山」を運営しているとうかがいました。
もともと地域おこし協力隊の任期が終わったら、「ファブラボ栗山」を町からの委託として運営していくことは決まっていました。役場の皆さんとも仲良くさせていただいていて、無事に合同会社を立ち上げ、委託事業を始められています。
会社の名前は「合同会社ジモトファブ」です。協力隊の同期の岡さんと2人で立ち上げました。
──社名の由来を教えてください。
「ファブ」とは「素晴らしい」という意味のファビュラスと、「ものづくり」という意味のファブリケーションを組み合わせた造語です。
僕たちは地域の人たちが町の課題をものづくりで解決する、楽しみながら町へ貢献できるような拠点をつくりたい。栗山町だけに留まらずに、地元を盛り上げたいという色々な町の人と連携しながらものづくりの素晴らしさを広めていきたい。そんな思いから、「ジモトファブ」という名前にしました。
──「ジモトファブ」の事業内容を教えてください。
メインは栗山町役場からの委託事業である「ファブラボ栗山」の運営です。僕らが行っていきたいのは、デザインの代行事業とプログラミングやデザインの教室事業。
5年目くらいからは、ファブキャラバン事業を始めたくて。ファブラボを道内で拡大していくようなことをやっていきたいんです。
現状は、僕と岡さんの2人で運営しているので、事業を拡大したり、まちの外に出ていくのはまだまだ難しいです。なので最初の数年間は、次の担い手の育成にも力を入れながら、自分たちの活動の土台を作っていこうと思っています。
──これからどんどんジモトファブによって、ものづくりできる人が増えていきそうですね。
ジモトファブが事業を通して大事にしていることはありますか?
「まちの未来を開拓する担い手づくり」っていうのが工房のコンセプトでやっています。
工房にある機材は「手段」でしかないんです。栗山町に住む人たちのアイデアや視点は、ものづくりを通して具現化することで地域の課題解決につながるかもしれない。
ファブラボで得たものづくりのスキルで地域を盛り上げられる人が増えれば、外の力に頼らないでまちを盛り上げられると思うんです。
「自分たちのまちのことは、なるべく自分たちで良くしよう」という空気感を育てていきたい。
そんな未来を実現すべく、週に1度町民向けに無料でラボを開放しています。工房でどんなものづくりができるのかとか相談会とか、気軽に参加できるイベントなども行っていますよ。
デザインは誰かのためにあるもの
──土山さんが、創造するときに大切にしていることはありますか。
デザインは自分のためではなく、「誰かのために」が根本にあるかもしれません。
工房にまちの人が来たときには、どんなものを作りたいか、何を解決したいか、相談に乗るんです。じっくり時間をかけながら一緒に作っていって、その人が満足するものが出来上がったときはやっぱり嬉しい。誰かのサポートをすることがやりがいです。
──相手のためを思ってつくることで自分が想像もしていなかった作品が生まれることはありますか?
いつも想像はできていません。なぜなら、僕が欲しいものではなくて、その人が欲しいものだから。相手と話し合いを重ねて、相手が喜んでくれるものを作ろうと意識してます。もしこの人と同じ立場になったとき、「自分も欲しい」と思えるものをつくってます。
この前、リウマチで車いすを利用している方のブレーキハンドルをつくったんです。その方から話を聞くと、ブレーキのレバーが細すぎても握れないし、太すぎても力が入らないとのこと。
利用者の目線に立って、改良に改良を重ねました。最終的に、作ったハンドルでその方が軽い力でもラクラクとブレーキをかけれるようになったんです。
ハンドルの付いた車椅子は今でも施設で他の人に受け継がれているようでして。この話を聞いた時は感動しましたね。
──相手にとことん寄り添える、良き伴走者なんですね。
寄り添える人に憧れはありますね。「土山さんに聞けば何か解決策をくれそう」って思われる人になりたいと思っています。僕以外にも関わってくれている協力隊も、寄り添える人です。そういう人が一人でも多く工房にいることが大切だと思いますね。
ものづくりって、なんとなく難しそうというイメージを抱きがちなんですが、工房にいる僕が親身にものづくりの伴走をしていけば、一度来てくれた人もまた来てくれるのかなって。ハードルを下げることはずっと意識しています。
──ハードルを下げたいという思いは、いつから。
元々はそれほど強くなかったです。ファブラボに来てから変わりましたね。まちの課題を解決したり、ものづくりを根付かせるためには、イベントのようなその場限りの取り組みでは限界がある。
定期的にまちの人が来てくれるようにするためにはやっぱり、ものづくりのハードルを下げて身近に感じてもらうことが必要だと思っています。そして徐々にものづくりの土壌をつくっていきたいですね。
ゴールに辿り着くまでの成功も失敗も残したい
──最後に、土山さんが未来に残したいものはなんですか。
ファブラボの存在価値の一つとして、「知の集積」があります。知見や知識が集約されて保管されていく、これを残したい。
デザインやものづくりって、作品としてできたものは形として残っていきやすい。でも、完成に至るまでのプロセスはかんたんに消えていってしまう。ファブラボでは、完成するまでにあった失敗や成功も全部記録して残していくという考えで活動しているんです。
課題解決に取り組むときに、失敗や成功の事例が残っていれば、よりよい課題解決につながるかもしれない。可視化されていることへの安心感もあるし、スピード感のある課題解決もできるかもしれません。
もし僕がこの地を離れたとしても、失敗談や経験談が残されていれば、僕の思いが誰かに引き継がれていくかもしれない。それが未来に残り続けて、次の世代の人たちにも伝わっていってほしいですね。
■ファブラボ栗山
住所:〒069-1511 北海道夕張郡栗山町中央3丁目154番地1 栗山煉瓦創庫くりふと 栗山駅南交流拠点施設
WEBサイト:https://fablabkuriyama.jp/equipment.html
▼各SNS